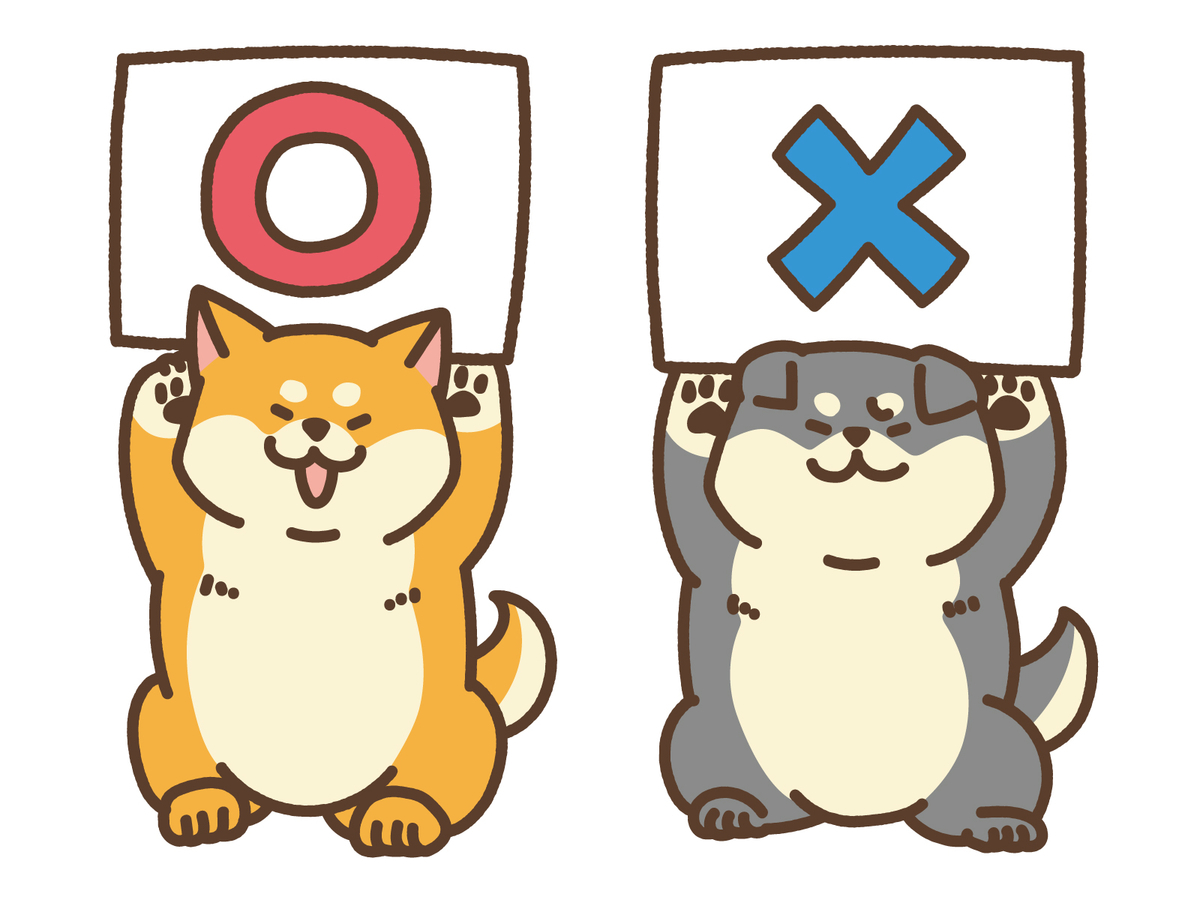
言葉って難しい。しえるです。
私は校正に関わるお仕事をいろいろしてきましたが、校正の仕事をしていると自分には思いつきもしない言葉の使われ方がたくさん出てくるので、言葉の意味について深く考えさせられることが多く、とても勉強になります。
私自身間違えていたなぁと気づかされたこともありますし、100%正しい日本語なんて不可能だと思いますが、今回は「本当はこっちなはずなんだけどなぁ~」とよく感じる日本語のお話です。
校正していて間違いが多いと感じる日本語の話。
「恐れ」
よく使われる表現として「~のおそれがある」というものがありますが、この場合の「おそれ」は心配や懸念ですので、本来は「虞(おそれ)」となります。
たとえば「事故のおそれがある」は、「事故をこわがる」ではなく「事故を懸念する」ですよね。
と言っても「虞」を読める人はおそらく多くはないでしょうし、「恐れ」を使う人が多いとも思いますので、「恐れ」がほぼ定着していると言っても過言ではない現状ではあります。
もちろん「こわがる」の意味であれば「恐れ」で問題ありません。
個人的には懸念の意味で使うときに「おそれ」とひらながにされているのを見かけると、ちゃんと理解して使っているのかなと感じます。
「排水口」「排水溝」
これは漢字が表すとおりなのですが、「口=あな」「溝=みぞ」の意味を持っています。
つまり、キッチンや風呂場などにある穴が「排水口」、道路脇などにある細長いくぼみの水路が「排水溝」となり、物がまったく違います。
家の中で掃除に苦戦するのはだいたい、狭い穴状である「排水口」でしょう。
「固定概念」
まず「観念」とは個人的な考えを指すのに対し、「概念」は対象の物事がどんなものであるか基本的な特徴をまとめた定義のようなもので、共通認識となります。
ということはつまり、「概念」は個人によって簡単に左右されるものではありません。
「固定概念」という言葉が「自分の中での当たり前の感覚にしばられる」といった意味で使われがちですが、「自分が物事をどう捉えるのか」というのは個人的な話となるので「固定観念」が正しいということになります。
そもそも多くの「観念」で固定されたものが「概念」であり、もし概念という言葉を使いたいのであれば、「既成概念」が近いのではないでしょうか。
この世界というのは先に事象(観察しうる形をとって現れる事柄)があって、それに対し人間が調べたり考えたりすることで認識して、皆がそれと共通認識できるように名づけられてきたもので現在成り立っています。
それでも「パラダイムシフト」という言葉があるとおり、時代によって物事に対する認識がガラッと変わることも多々ありますね。
今ある当たり前を疑うのが難しかったとしても、10年前や100年前の感覚に対して「何それ~理解できない」と感じることはあるものではないでしょうか。
であれば10年先100年先には様変わりして、今の感覚が笑い話になっていることもいくらだって起こりえる話です。
こういった今の社会を構成しているものは「既成概念」であり、それが皆、正確であるとは限りませんので、「既成概念」が変わる可能性もいくらでもあり得るでしょう。
今回書いたこともあくまで「既成概念」だと思いますので、もしかしたら今後変わる可能性もあるかもしれませんが、とりあえず現時点では違うんじゃないかなっていう話でした。
